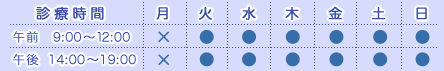Orthomed社(イギリス)から、2007年に発売されたロッキングプレートです。2006年にスペインで開催されたECVSにおいて先行展示されており、「極度に破綻した人工関節の修復時に良いのでは?」と考え、発売と同時に導入しました。しかしながら、当院では現在、SOPによる補助を必要とするような重篤な人工関節全置換術の合併症の経験はなく、骨折症例のみへの使用となっています。日本国内では販売されていないため、農林水産省に個人輸入確認願いを提出し個人輸入しています。2007年前後から、獣医学領域においても各社からロッキングプレートが発売されており、今後の普及が予想されます。
2007年に米国でTPLO用プレートの発売が開始され、TPLOプレートを導入しました。これに伴い、LCPを導入しました。日本では、2008年から日本シンセスがSynthes LCP & TPLO Seminarなどの幾つかの講習会を開催しており、受講者にLCPが販売されています。
当院では2002年に導入した創外固定装置で、Medical Solution(スイス)から販売されています。フランスの医学領域で、戦時中に兵士の指の骨の骨折を治療するために考案・開発されたものです。チューリッヒ大学では、超小型犬種の橈尺骨骨折などの治療に使用されていました。当院では、超小型犬種の橈尺骨骨折や脛骨の骨折に使用してきました。同システムは日本国内では販売されていないため、農林水産省に個人輸入確認願いを提出し個人輸入しています。日本国内では、2011年頃から販売が開始されるようです。
当院では2001年に導入した髄内釘で、ドイツのVolker Hachが考案し、ROTECH社(ドイツ)から販売されています。日本国内では販売されていないため、農林水産省に個人輸入確認願いを提出し個人輸入しています。インターロッキングネイルと同じく、後肢では大腿骨や脛骨、前肢では上腕骨の骨折に使用します。インターロッキングネイルに比して、ジグなどを装着する必要がないため、手術時間を短縮できるという利点や症例に応じた長さに切ることが可能という利点を有しています。
当院では1999年に導入したInnovative社(米国)の髄内釘です。インターロッキングネイルは、ヒトの整形外科においても多く用いられる固定法です。インターロッキングネイルを骨髄内に挿入し、骨折片の近位と遠位をロッキングボルトやスクリューで固定します。後肢では大腿骨や脛骨、前肢では上腕骨の骨折に使用します。現在、数社のシステムが販売されていますが、Innovative社のシステムは2007年に国内での販売が開始されています。
膝関節は、大腿骨と脛骨、膝蓋骨から構成されています。脛骨の上を大腿骨の丸い先端が滑り転がるように動いています。滑り転がるように運動するため、靭帯や半月板が膝関節を安定化させるために重要な役割を果たしています。
前十字靭帯(Anterior Cruciate Ligament:ACL)は膝関節を安定化させているロープの様な構造で、前内側帯(craniomedial band:CMB)と後外側帯(caudolateral band:CLB)の2つより構成されています。犬の前十字靭帯断裂は発生頻度の高い整形外科疾患で、1歳齢を超えた殆どの犬種において後肢跛行の原因として経験されます。
前十字靭帯の部分断裂もしくは完全断裂が起こると、種々の程度の膝関節の不安定性、疼痛、滑膜炎が発現し、不安定性の放置は二次性の変形性関節症や半月板損傷を招きます。
- 脛骨の前方変位の抑制
- 脛骨の内旋の制限
- 膝関節の過伸展の防止

前十字靭帯(青矢印)、後前十字靭帯(緑矢印)、半月板(紫矢印)

前十字靭帯(青矢印)、後前十字靭帯(緑矢印)、半月板(紫矢印)、膝蓋骨(赤矢印)、大腿骨(橙矢印)、脛骨(茶矢印)。

ラブラドール・レトリバー、3歳齢の右膝関節。
前十字靭帯(ACL)、後前十字靭帯(PCL)、前内側帯(水色点線)、後外側帯(赤点線)

ラブラドール・レトリバー、3歳齢の右膝関節。
前十字靭帯(ACL)、後前十字靭帯(PCL)。関節内探索用のプローブ(黄色矢印)にて後十字靭帯を避けて、前十字靭帯のみを観察しています。

ラブラドール・レトリバー、3歳齢の右膝関節。
異常のない半月板がみられます。
半月板は大腿骨と脛骨の関節面をフィットさせる機能をもちクッションの役割をはたしています。
前十字靭帯断裂による関節の不安定性が持続すると半月板損傷を招きます。
- 歩き方がおかしい、おかしい時がある
- 左右不明であるが、歩き方がおかしい
- 最近、散歩を嫌がる
- ボール遊び中などに、急に“キャン”と鳴いてから後肢挙上、後肢を引きづる
- 散歩中、他の犬にじゃれつかれて、じゃれつこうとして“キャン”と鳴いてから後肢挙上、後肢を引きづる
- 庭などで遊ばしていたら、気がついたら後肢挙上
- 膝が腫れてきた ・ 若齢時より股関節形成不全(CHD)で、中・高齢になり急に歩き方がおかしくなった
- 時々、後肢の挙上や跛行を示すが、数日で改善する
- 主訴、歩様の確認、視診、触診
- 前方引き出し検査(cranial drawer test)
- 脛骨圧迫試験(tibial compression test)
- 関節包内側の線維性肥厚(medial buttress)
- お座り試験(sit test)
- 関節液細胞診検査(単核細胞の増加)
- X線検査(関節液増量像、脛骨の前方変位、骨増殖体などの変性性変化)
- フォースプレート歩行解析(当院では可能ですが、一般的には行われません)
- 関節鏡検査
- CT検査
●股関節形成不全(CHD)
●膝蓋骨脱臼
●腫瘍性疾患








●脛骨矯正骨切り術
TPLO(脛骨高平部水平化骨切り術)

aCBLO(CORAによる水平化骨切り術)


TTA(脛骨粗面前進化術)

●LSS(関節外安定化術)



●小型犬・猫の前十字靭帯断裂
※当サイトに掲載されている写真、イラストの無断転用及び転載を一切禁止します。